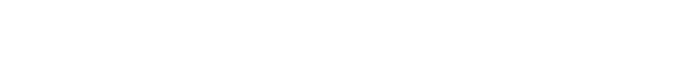- 【🐈 里親募集のお知らせ】
- 2025年6月21日
【🐈 里親募集のお知らせ】


香川県の猫多頭飼育崩壊現場から
大森ペット霊堂にやってきました『お喋り』と『ぶる男』です🐈
『お喋り』🐈
推定3歳から5歳ほどの女の子
マイペースな性格で甘えん坊😂
ベビたちの育児をし、時には自分のお気に入り場所で休み、スタッフに甘え。
一日のルーティンがしっかりしていてマイペースな子です。
お喋りは高い場所でゆっくり過ごすのが好きみたいで
新しいことにも興味津々、新しい家庭でもたくさんの
笑顔をくださることと思います。


『ぶる男』🐈⬛
推定6歳から8歳ほどの男の子
クールな性格なのに、甘えん坊😁
撫でて触って攻撃が止まらず、初日からスタッフたちの心を射止めました。
よく寝て、よく甘えて。
遊ぶの好きじゃないのかなあと思いきや
ヘアゴムで遊び😂
テーブルの下や物陰が好きで1人時間も上手に過ごせます。


お喋りとぶる男の残りのにゃん生を見守り、
たくさんの楽しい思い出を作ってくださるご家族様を探しています。🐈
少しでも2匹に惹かれた方は、インスタグラムのDM、またはお電話やメールにて
ご連絡くださいませ。
___________________________
大森ペット霊堂
〜考えるのは、いのち。〜
🐕住所:東京都大田区大森東2-1-1
📞電話:03-3763-6300
✉️メール:service@petsougi.jp
🚃アクセス:京急平和島駅から徒歩10分