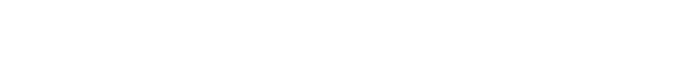農作物と動物の関係|被害の実態と効果的な対策方法
2025年9月25日

農作物を育てるうえで大きな課題となるのが、動物による食害や掘り起こし被害です。シカやイノシシといった大型の野生動物から、カラスやスズメなどの鳥類、さらにはネズミやモグラなどの小動物まで、農作物に悪影響を与える存在は数多くいます。
本記事では「農作物に影響を与える代表的な動物」と「被害を防ぐための具体的な対策」をわかりやすく紹介します。農業を営む方はもちろん、家庭菜園を楽しむ方にも役立つ内容です。
目次
農作物に影響を与える動物とは?
野生動物による農作物被害
農地を荒らす代表的な動物が シカ・イノシシ・サル です。
-
シカ は葉や芽を食べ尽くすため、成長途中の作物が被害を受けやすい傾向があります。
-
イノシシ は畑を掘り返し、芋類や根菜を食べるだけでなく、農地を荒らしてしまうことが大きな問題です。
-
サル は果樹や野菜を狙い、群れで行動するため被害が大きくなることがあります。
鳥類による農作物への影響
-
カラス は収穫前のトウモロコシやスイカなどを狙います。
-
ヒヨドリやスズメ は小さな果実や稲穂を食べ、農作物全体に広範囲の被害を与えることがあります。
小動物・害獣による被害
-
ネズミ は収穫物だけでなく、保管中の農作物も食べてしまいます。
-
モグラ は直接農作物を食べるわけではありませんが、穴を掘ることで根を傷め、栽培環境を悪化させます。

農作物を守るための対策方法
物理的な対策
もっとも一般的なのが 防護柵や電気柵 の設置です。これにより大型動物の侵入を防ぐことができます。また、防鳥ネットや防鳥糸 を利用することで、小鳥から農作物を守ることも可能です。
動物の習性を利用した対策
音や光を利用した忌避装置も有効です。
-
センサーで動くライトや音を発する装置
-
天敵の匂いや模造物(フクロウの模型など)
を設置することで、動物に「危険な場所」と認識させます。
栽培方法の工夫
-
動物が嫌う植物を周囲に植える「混植」
-
作付けの時期を調整して、被害の多い季節を避ける
といった工夫も効果的です。

農作物と動物の共生を考える
地域ぐるみでの被害対策
一人の農家だけでは被害を防ぎきれない場合があります。地域全体で情報を共有し、農業組合や自治体の支援制度を活用することで、効率的な対策が可能になります。
動物保護と農業のバランス
農作物を守るために動物を駆除するだけでは、自然とのバランスを崩してしまう恐れがあります。地域によっては、動物を追い払いながら農業を続ける「共生」の取り組みも進められています。

まとめ
-
農作物に影響を与える動物はシカ・イノシシ・サル・カラス・ネズミなど多岐にわたる。
-
防護柵やネット、忌避装置など複数の方法を組み合わせることが重要。
-
農作物を守ることと、動物との共生を両立させる視点が、持続可能な農業につながる。
よくある質問
Q1.農作物に最も被害を与える動物は何ですか?
地域によって異なりますが、日本では シカ・イノシシ・サル が三大害獣と呼ばれ、深刻な被害を与えています。特に山間部ではシカやイノシシ、果樹園ではサルによる被害が目立ちます。
Q2.鳥による農作物被害はどう防げますか?
防鳥ネットや防鳥糸の設置 が有効です。さらに、フクロウやカラスの模型、反射テープなど視覚的に威嚇する方法を組み合わせることで効果が高まります。
Q3.電気柵は本当に効果がありますか?
はい。正しく設置すればシカやイノシシの侵入を大幅に減らせます。ただし、草が柵に触れると電気が流れにくくなるため、定期的なメンテナンスが必要です。
Q4.動物を駆除せずに農作物を守る方法はありますか?
あります。忌避装置・混植・作付け時期の工夫 などで被害を減らすことが可能です。また、地域全体で取り組むことで、動物を追い払いながら共生する方法も広がっています。
Q5.農作物を守るために犬を活用することはできますか?
はい。牧羊犬や番犬のように、犬は農作物を荒らすシカやイノシシを追い払う役割を果たすことがあります。特に農村地域では、犬の存在自体が野生動物への抑止力となります。ただし、犬が畑に入り込み農作物を踏んでしまうこともあるため、訓練や管理が必要です。
wp-tech
最新記事 by wp-tech (全て見る)
- 猫編:ペットロスを癒す映画|大切な猫を失った心に、そっと寄り添う物語 - 2026年2月15日
- 犬編:ペットロスを癒す映画|大切な犬を想うあなたへ、心に寄り添う作品 - 2026年2月13日
- トリマーとはどういう仕事?仕事内容・資格・向いている人を解説 - 2026年2月11日