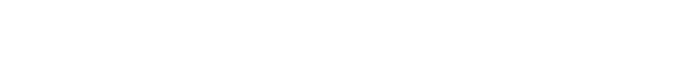殺処分が多い県はどこ?最新ランキングと背景・対策を徹底解説
2025年11月19日

日本では、ペットとしての犬・猫を含め、年間数万頭に上る動物が行政施設などで殺処分されてきました。近年その数は減少傾向にありますが、都道府県ごとには大きな差があります。
では、「どの県で殺処分が多いのか」を最新データから見て、その背景と私たちにできることを整理していきましょう。
目次
- 1.「殺処分」とは?基本の意味と現状を知ろう
- 2.殺処分が多い県ランキング【最新データ】
- ⚫︎犬
- ⚫︎猫
- ⚫︎犬猫合計数
- 3.なぜ殺処分が多いのか?3つの主な要因
- 4.殺処分を減らすために行われている取り組み
- 5.私たちにできること:飼い主・市民としての行動
- まとめ:殺処分を減らすには、社会全体の意識がカギ
- よくある質問(FAQ)
- Q1.なぜ県によって殺処分数に差があるのですか?
- Q2.「殺処分ゼロ」を達成した県はありますか?
- Q3.殺処分の多い県ではどんな改善策が取られていますか?
- Q4.動物の殺処分はどうやって行われているのですか?
- Q5.私たちができる具体的な行動は何ですか?
- Q6.自治体や団体を支援する方法はありますか?
1.「殺処分」とは?基本の意味と現状を知ろう
犬・猫の「殺処分」とは、飼い主不明・飼育放棄・野良化などで引き取られたあと、返還・譲渡ができずに処分された動物を指します。たとえば、最新の国の統計では、令和5年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における犬・猫の殺処分数は計 9,017 頭でした。(環境省統計資料参照)
ただし「数が少ない=課題がない」というわけではなく、都道府県単位での差が依然として大きい点に注目です。
2.殺処分が多い県ランキング【最新データ】
以下は、環境省発表の資料により「殺処分数」が多い傾向がある県のランキングです。
⚫︎犬
- 1.徳島県
2.香川県
3.長崎県
4.愛媛県
5.愛知県
6.千葉県
7.熊本県
8.広島県
9.大分県
10.滋賀県、10.鹿児島県
⚫︎猫
- 1.福島県
2.岐阜県
3.秋田県
4.奈良県
5.長崎県
6.兵庫県
7.大分県
8.青森県
9.愛媛県
10.和歌山県
⚫︎犬猫合計数
- 1.福島県
2.長崎県
3.岐阜県
4.秋田県
5.愛媛県
6.大分県
7.奈良県
8.兵庫県
9.青森県
10.香川県
このように、北から南、人口・環境が異なる県で差があるのは注目すべき現象です。

3.なぜ殺処分が多いのか?3つの主な要因
-
・飼育放棄・迷い犬猫・野良化の多さ
特に野外に放されたり、飼い主のいない動物の収容が多い地域では、処分に至る割合も上がります。 -
・譲渡・返還体制の地域格差
例えば譲渡数の少なさ、譲渡先を探す体制・ネットワークの弱さが殺処分を減らせない原因となります。 -
・行政施設のキャパシティ・対応力の違い
収容施設が整っていなかったり、費用・人手が足りなかったりする県では、処分に頼らざるを得ない状況も報告されています。
4.殺処分を減らすために行われている取り組み
-
・自治体による譲渡会・ボランティア団体との連携強化
-
・野良化防止としてのTNR(捕獲・不妊去勢・再放出)活動
-
・飼い主向けの啓発や法令改正(販売規制・マイクロチップ義務化など)
こうした取り組みが奏功して、処分数の減少に繋がっている例もあります。
5.私たちにできること:飼い主・市民としての行動
-
・ペットを飼う前に「終生飼養」の責任を考える
-
・譲渡可能な動物を検討する、里親制度を知る
-
・地域猫活動・TNR活動に関心を持ち、情報発信や寄付・ボランティアを行う
こうした身近な行動が全体の流れを変える第一歩となります。
まとめ:殺処分を減らすには、社会全体の意識がカギ

データが示す通り、都道府県によって「殺処分の多さ」の背景には様々な構造的要因があります。数値だけで終わらせず、命に向き合う意識を持つことが、減少に向けた本当の一歩です。私たち一人ひとりの「選択」が、動物たちの未来を変える力となります。
よくある質問(FAQ)
Q1.なぜ県によって殺処分数に差があるのですか?
飼育放棄や野良化の多さ、譲渡体制・施設の整備状況、ボランティア団体との連携度などが異なるためです。
Q2.「殺処分ゼロ」を達成した県はありますか?
熊本県や神奈川県などは、行政と民間の協働によって犬の殺処分ゼロを達成した年度があります。
Q3.殺処分の多い県ではどんな改善策が取られていますか?
譲渡会やSNS発信の強化、地域ボランティアとの連携、TNR活動の推進などが進められています。
Q4.動物の殺処分はどうやって行われているのですか?
多くの自治体では、動物福祉に配慮した方法(麻酔ガスなど)を採用していますが、痛みや恐怖を完全に排除するのは難しく、課題が残っています。
Q5.私たちができる具体的な行動は何ですか?
ペットを迎える前に責任を持つ覚悟をし、里親制度や地域猫活動に関心を持つことが大切です。
Q6.自治体や団体を支援する方法はありますか?
寄付・ボランティア・SNSでの発信・譲渡会のシェアなど、支援の形は多様です。地域の動物愛護センターの活動情報を確認しましょう。
wp-tech
最新記事 by wp-tech (全て見る)
- 犬・猫アレルギーの人でもペットと暮らせる?原因と対策を徹底解説 - 2026年2月23日
- 歴史がある犬種とは?古代から人と共に歩んできた犬たち - 2026年2月21日
- マルチーズの寿命は何歳?平均寿命・長生きの秘訣と注意点を解説 - 2026年2月19日