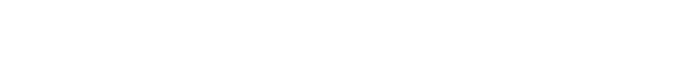野良猫を保護する方法と注意点|保護後のケアや里親探しまで徹底解説
2025年9月29日

「野良猫を保護したいけれど、どうすればいいの?」
そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。野良猫は厳しい環境で生きており、怪我や病気にかかるリスクも高いため、保護することは猫の命を救う大切な行動です。
しかし、やみくもに保護してしまうと猫に強いストレスを与えたり、思わぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、野良猫を保護する前に知っておくべきことから、保護の方法、保護後のケア、さらに里親探しや地域猫活動まで、わかりやすく解説します。
目次
- 1.野良猫を保護する前に知っておきたいこと
- 野良猫と地域猫の違い
- むやみに捕まえない方がいいケース
- 保護する前に確認すべき法律・地域ルール
- 2.野良猫を保護する方法
- 捕獲のタイミングと注意点
- 捕獲器の使い方とレンタル先
- 怪我や病気の猫を見つけたときの対応
- 3.野良猫を保護した後の流れ
- 動物病院での健康チェック
- 一時的な預かり環境を整える
- 心を開いてもらうための接し方
- 4.里親を探す方法
- 里親募集サイトやSNSの活用
- 譲渡会に参加する
- 里親に引き渡す際の注意点
- 5.自分で飼う場合に必要な準備
- 猫を飼うための初期費用と継続費用
- 室内飼育に必要なグッズ一覧
- 先住猫や犬がいる家庭での注意点
- 6.地域猫活動とTNR(捕獲・不妊手術・元の場所へ戻す)
- 地域でできる猫の保護活動
- ボランティア団体や行政との連携方法
- まとめ
- よくある質問
- Q1.野良猫を保護したら、まず何をすべきですか?
- Q2.野良猫を家に迎え入れるとき、どのくらいで慣れますか?
- Q3.保護した野良猫を里親に出す際、必要な手続きはありますか?
- Q4.野良猫を保護するお金がないときはどうすればいいですか?
- Q5.犬を飼っている家庭でも野良猫を保護できますか?
1.野良猫を保護する前に知っておきたいこと
野良猫と地域猫の違い
野良猫は飼い主のいない猫を指しますが、地域猫は自治体や住民の合意のもとで世話をされている猫です。地域猫の場合は勝手に保護せず、地域や団体に相談する必要があります。
むやみに捕まえない方がいいケース
攻撃的な猫や病気が重い猫は、専門家や動物愛護団体の協力が必要です。無理に捕まえると猫にも人にも危険が及ぶ可能性があります。
保護する前に確認すべき法律・地域ルール
一部の自治体では捕獲や飼育に届け出が必要な場合があります。動物愛護センターや保健所に確認しておきましょう。

2.野良猫を保護する方法
捕獲のタイミングと注意点
猫が落ち着いている時間帯(早朝や夜)に行うのが効果的です。急な大声や動きは避け、猫のストレスを最小限にしましょう。
捕獲器の使い方とレンタル先
捕獲器は動物病院や保護団体で借りることができます。餌で誘導し、捕獲できたらすぐに布をかけて落ち着かせてください。
怪我や病気の猫を見つけたときの対応
明らかに重症の場合は、自分で動かさず、すぐに動物病院や保護団体に連絡を。感染症のリスクがあるため、素手で触るのは避けましょう。

3.野良猫を保護した後の流れ
動物病院での健康チェック
ワクチン接種、不妊手術、ウイルス検査(猫エイズ・白血病)は必ず受けましょう。これにより今後の飼育方針が決まります。
一時的な預かり環境を整える
静かな部屋にケージを用意し、水・トイレ・餌を揃えます。最初は触らず、安心できる距離感を保つことが大切です。
心を開いてもらうための接し方
急に触ろうとせず、時間をかけて慣れてもらいましょう。柔らかい声で話しかけたり、少しずつ距離を縮めて信頼関係を築きます。

4.里親を探す方法
里親募集サイトやSNSの活用
「ペットのおうち」や「ジモティー」などのサイトを利用する人も多いです。写真や性格を丁寧に紹介するのがポイントです。
譲渡会に参加する
地域の愛護団体が主催する譲渡会に参加すれば、里親希望者と直接会えます。安心して引き渡せる可能性が高まります。
里親に引き渡す際の注意点
譲渡契約書を作成し、終生飼育や不妊手術を約束してもらうことが大切です。

5.自分で飼う場合に必要な準備
猫を飼うための初期費用と継続費用
初期費用は約3〜5万円、毎月の飼育費は5,000〜10,000円程度が目安です。
室内飼育に必要なグッズ一覧
キャットタワー、トイレ、爪とぎ、食器、キャリーケースなどを揃えましょう。
先住猫や犬がいる家庭での注意点
最初は隔離し、匂いや声に慣れてから少しずつ顔合わせするのが安心です。
6.地域猫活動とTNR(捕獲・不妊手術・元の場所へ戻す)
地域でできる猫の保護活動
給餌や清掃を住民で協力して行い、猫と人が共生できる環境を整える取り組みです。
ボランティア団体や行政との連携方法
TNR活動を行う団体や自治体と連携することで、地域全体の猫の繁殖制御につながります。
まとめ
-
野良猫を保護するには準備と安全な方法が必要
-
保護後は病院でのケアと環境整備を行う
-
里親探しか自分で飼うかを慎重に判断
-
地域猫活動やTNRも視野に入れると猫と人が幸せに暮らせる
よくある質問
Q1.野良猫を保護したら、まず何をすべきですか?
まずは動物病院に連れて行き、健康チェック(ワクチン・ウイルス検査・不妊手術)を受けさせることが最優先です。
Q2.野良猫を家に迎え入れるとき、どのくらいで慣れますか?
猫の性格によりますが、数日で慣れる子もいれば数か月かかる場合もあります。焦らず時間をかけることが大切です。
Q3.保護した野良猫を里親に出す際、必要な手続きはありますか?
譲渡契約書を交わし、終生飼育・不妊手術・ワクチン接種などを約束してもらうことをおすすめします。
Q4.野良猫を保護するお金がないときはどうすればいいですか?
動物愛護団体や自治体によっては、捕獲器の貸出や不妊手術の助成を受けられる場合があります。まずは地域の保健所やNPOに相談しましょう。
Q5.犬を飼っている家庭でも野良猫を保護できますか?
可能ですが、最初は必ず隔離が必要です。匂いや声に慣れてから少しずつ顔合わせをすることで、トラブルを防げます。
wp-tech
最新記事 by wp-tech (全て見る)
- 猫編:ペットロスを癒す映画|大切な猫を失った心に、そっと寄り添う物語 - 2026年2月15日
- 犬編:ペットロスを癒す映画|大切な犬を想うあなたへ、心に寄り添う作品 - 2026年2月13日
- トリマーとはどういう仕事?仕事内容・資格・向いている人を解説 - 2026年2月11日