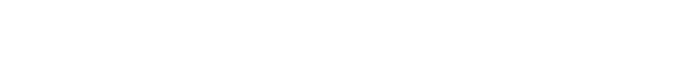【獣医師監修】猫の糖尿病。症状から治療まで完全ガイド
2025年8月10日

愛猫の健康を守るために知っておきたい重要な病気の一つが糖尿病です。人間と同じように、猫も糖尿病を発症することがあり、近年その発症率は増加傾向にあります。特に室内飼いの猫や肥満気味の猫では、糖尿病のリスクが高まることが知られています。この病気は初期症状が分かりにくく、気づいた時には既に進行していることも少なくありません。しかし、正しい知識を持ち、早期発見・適切な治療を行うことで、愛猫と長く幸せな時間を過ごすことは十分可能です。今回は、猫の糖尿病について、基本的な仕組みから症状の見極め方、治療法まで、飼い主として知っておくべき情報を詳しく解説していきます。愛猫の健康管理に役立てていただければと思います。
ブログ 医療監修
—————————————————————
監修:わんにゃん保健室 獣医師 江本 宏平
https://asakusa12.com
—————————————————————
目次
- 1. 猫の糖尿病とは?基本的な知識と仕組みを解説
- 1.1 糖尿病のメカニズム
- 1.2 猫の糖尿病の発症リスク
- 1.3 症状の特徴
- 2. 愛猫が糖尿病になりやすい原因と危険因子
- 肥満
- 年齢
- 去勢・避妊手術
- ストレス
- 食事の内容
- その他の要因
- 3. 見逃せない!猫の糖尿病の初期症状から末期症状まで
- 初期症状
- 進行した症状
- 末期症状
- 4. 動物病院での糖尿病の診断方法と検査内容
- 血液検査
- 尿検査
- 他の検査方法
- まとめ
- 5. 猫の糖尿病の治療法と効果的な食事管理
- インスリン療法
- 食事管理
- 環境への配慮
- まとめ
- よくある質問
- 猫の糖尿病の主な症状は何ですか?
- 猫の糖尿病の発症リスクはどのような要因がありますか?
- 猫の糖尿病の診断方法には何がありますか?
- 猫の糖尿病の治療法にはどのようなものがありますか?
1. 猫の糖尿病とは?基本的な知識と仕組みを解説
猫の糖尿病、正式には「糖尿病性ケトアシドーシス」とは、猫の体内で血液中のブドウ糖が異常に高い状態を指します。この状態は「高血糖」と呼ばれ、主に膵臓が正常なインスリンを分泌できないか、インスリンの作用が低下していることが原因です。インスリンは血糖値を調節するために欠かせないホルモンで、その不足から糖尿病を発症することがあります。
1.1 糖尿病のメカニズム
猫に最も一般的な糖尿病のタイプは「2型糖尿病」です。このタイプでは、体内にはインスリンが存在しますが、その働きが不十分です。その結果、細胞が血糖を十分に取り込めず、高血糖状態が長引くことになります。このような持続的な高血糖は、内臓や組織に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
- 糖の取り込み: 食べ物から得た糖は血液中に入りますが、インスリンが機能しないと細胞がそれを吸収できずに血中に留まります。
- 高血糖の状態: インスリンの量が足りないか、その効果が発揮されない場合には、細胞は糖を取り込めず、血中の糖が異常に増加します。
1.2 猫の糖尿病の発症リスク
猫が糖尿病を患う原因には多くの要因があります。
- 肥満: 特にオス猫は、与えられる食事の量を適切に管理しないと肥満が進みやすく、その結果糖尿病のリスクが高まります。
- 高齢: 年齢を重ねるとインスリン抵抗性が増し、それが糖尿病を引き起こす要因となることが多いです。
- 遺伝的要因: 一部の猫種は糖尿病にかかりやすい遺伝的素因を持っていると言われています。
1.3 症状の特徴
猫が糖尿病に罹患すると、以下のような特徴的な症状が見られます。
- 多飲多尿: 猫は普段以上に水分を摂取し、その結果尿の量も増加します。これは体が余分な糖を排出しようとする自然な反応です。
- 体重減少: 食欲があるにもかかわらず、体重が減少することがあります。これは、細胞に糖が供給されないために栄養不足が生じるためです。
- 元気がなくなる: エネルギー不足から猫の活力が低下し、運動量が減少することが見られます。
猫の糖尿病は、気を付けなければならない病気であり、人間における糖尿病と似た特徴を有しています。特に、肥満や高齢の猫において発症が多いことが知られています。早期診断と適切な治療が必要不可欠なため、飼い主は愛猫の健康状態を注意深く観察し、糖尿病の可能性を早期に察知することが重要です。猫の糖尿病についての知識を深めることで、愛するペットの健康を守るための大切なステップを踏むことができます。

2. 愛猫が糖尿病になりやすい原因と危険因子
猫の糖尿病は、さまざまな要因から発症するリスクが高まります。ここでは、愛猫が糖尿病になりやすい原因と危険因子について詳しくご紹介します。
肥満
猫の糖尿病の主な原因は肥満です。肥満の猫は、糖尿病のリスクが大幅に増加します。以下の点に特に注意してください。
- インスリン抵抗性: 肥満の猫はインスリンへの反応が鈍くなるため、血糖値の調整が難しくなります。
- 運動不足: 家の中で過ごすことが多い猫は運動不足になりやすく、これが肥満を引き起こし、糖尿病のリスクをさらに助長します。
年齢
猫の年齢も糖尿病の発症に大きな影響を与えます。特に中年以上の猫では、以下の理由からリスクが高まることがあります。
- インスリン分泌の減少: 年齢を重ねると、膵臓からのインスリン分泌が減少し、血糖値の管理が難しくなることがあります。
- 代謝の変化: 加齢に伴い、代謝が低下し、体重管理が困難になることで肥満が進行することがあります。
去勢・避妊手術
去勢や避妊手術を受けた猫は、ホルモンバランスの変動により体重が増加しやすく、それが糖尿病のリスクを引き上げます。手術後は特に食事管理に注意が必要です。
ストレス
ストレスも猫の糖尿病の要因の一つです。ストレスを感じる猫には以下のような変化が見られます。
- 血糖値の変動: ストレスがかかるとストレスホルモンが体内で増加し、血糖値が上昇します。
- 食欲の変化: ストレスによって食欲が乱れ、過食や運動不足を引き起こし、結果的に肥満を招くことがあります。
食事の内容
猫の食事内容も、糖尿病のリスクに深く関わっています。特に高炭水化物の食事は糖尿病を引き起こす可能性が高まります。猫は肉食動物であるため、以下の点に気を付けることが重要です。
- 高炭水化物食: 炭水化物を多く含む食事は血糖値を急激に上昇させ、糖尿病のリスクを増加させます。
- 適切な栄養管理: 高タンパク質・低炭水化物の食事が推奨されており、血糖のコントロールがしやすくなります。
その他の要因
猫の糖尿病には、ウイルス感染やホルモンの異常も関与しています。以下のような条件がリスク因子となることもあります。
- 遺伝的要因: 一部の猫種は糖尿病にかかりやすいとされています。
- 既往歴: 膵炎や甲状腺機能亢進症などの過去にかかった疾患が、糖尿病のリスクを高める可能性があります。
これらの要因を理解し、愛猫の健康管理に役立てることで、糖尿病の予防に繋がります。日々の生活習慣や食事内容を見直し、愛猫の糖尿病予防に努めましょう。

3. 見逃せない!猫の糖尿病の初期症状から末期症状まで
猫の糖尿病は、早期発見が非常に重要です。初期症状に気づかずにいると、病状は急速に進行し、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。以下では、初期症状から末期症状までを詳しく見ていきましょう。
初期症状
猫の糖尿病の初期段階では、明確な症状が見られないことが多く、飼い主が気づくのが難しい場合があります。しかし、以下のサインには注意が必要です。
- 多飲多尿: 猫がいつもより水をよく飲み、トイレの回数も増える。
- 食欲の変化: 普段よりも食欲が増すが、体重が減ることがある。
- 元気の低下: 以前は活発だった猫が、だんだんと無気力になることがある。
これらの初期症状はしばしば見逃されやすく、特に飼い主が普段から環境を観察していない場合、糖尿病の進行を許す原因となります。
進行した症状
初期症状が放置されると、状態は悪化し、以下のような進行した症状が現れます。
- 体重減少: あまり食べていないはずなのに、体重が減少することが見られる。
- 嘔吐や下痢: 消化不良や肝機能の障害が原因で、嘔吐や下痢が発生する可能性がある。
- 毛並みの悪化: 毛がパサつき、つやが失われる。
これらの症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談することが重要です。
末期症状
糖尿病が進行すると、さらに深刻な末期症状が現れます。この段階では、以下のような症状が現れます。
- ふらつきやけいれん: 神経障害が進行し、歩行が不安定になることがある。
- 昏睡や呼吸困難: 生命の危機を伴う状態にもなるため、緊急の処置が必要。
- 食欲不振: 最終的には、食事を取ることができなくなることもある。
末期症状に達すると、治療の難易度が格段に上がります。このため、早期の段階での発見と介入は極めて重要です。
愛猫が健康でいるためには、これらの症状をよく観察し、異変に気づいた際には必ず獣医に相談することをお勧めします。特に、糖尿病のリスクがある猫では、日常的なケアと観察が欠かせません。

4. 動物病院での糖尿病の診断方法と検査内容
猫の糖尿病の早期発見は、治療の選択肢を広げ、健康管理に大きな役割を果たします。そのため、動物病院で行われる各種の診断検査が非常に重要です。ここでは、主要な診断方法とそれに伴う詳しい検査内容について解説します。
血液検査
猫の糖尿病を検出するための最も基本的で重要な手段が血液検査です。この検査では、以下のいくつかの重要な数値を評価します。
- 血糖値:糖尿病がある猫では、通常の血糖値よりも著しく高くなることがあります。健康な猫の血糖値はおおよそ100mg/dLですが、糖尿病の可能性がある場合には、500mg/dLを超えることも少なくありません。
- フルクトサミン値:この指標は、過去1〜2週間の平均血糖値を反映し、長期間にわたる高血糖の状態を確認するのに有用です。
尿検査
尿検査も猫の糖尿病診断において非常に役立つ検査です。この検査では、以下のようなポイントを確認します。
- 尿糖:糖尿病を持った猫の尿には、腎臓で処理されなかった血糖が尿に出るため、尿に糖が含まれ、「尿糖陽性」という結果が得られます。
- ケトン体:尿検査では、ケトン体の存在も重要な指標です。糖がエネルギー源として効率的に使われていない場合、ケトン体が多くなります。これも糖尿病の進行を示すサインとなります。
他の検査方法
糖尿病の診断のためには、以下の追加検査も実施されることがあります。
- 全身の血液検査:猫の糖尿病の原因を理解するために、膵炎や感染の有無を調べることで、詳細な情報を得ることができます。
- レントゲン検査:内部の器官を確認し、別の潜在的な健康問題の有無を調べます。
- エコー検査:主に膵臓やお腹の臓器に異常がないかを確認する目的で、頻繁に行われます。
まとめ
これらの検査を通じて、獣医師は猫の糖尿病を正確に診断することができます。特に、血液検査と尿検査は重要であり、迅速な結果を得るためには早めに動物病院を受診することが推奨されます。糖尿病の早期発見は、愛猫の健康を守るためには欠かせないものですので、日頃から注意深く観察することが重要です。

5. 猫の糖尿病の治療法と効果的な食事管理
猫の糖尿病を管理するためには、「インスリン療法」と「食事管理」の2つが重要なアプローチとなります。これらの方法を通じて、猫の血糖値を適切にコントロールし、健康なライフスタイルを維持することが可能です。
インスリン療法
猫が糖尿病にかかると、体内で必要量のインスリンが生成されなかったり、その効果が不十分になったりすることがあります。そのため、適切な状況下で外部からインスリンを投与する必要があります。効果的なインスリン療法を行うために、以下のポイントに留意しましょう。
- 投与方法: 通常、インスリンは皮下注射で行われ、飼い主が自宅で1日2回投与することが一般的です。
- 量の調整: 各猫の健康状態に応じて投与するインスリンの量は異なるため、定期的な血液検査を実施して、適切な量を見極めることが大切です。
- 副作用の観察: インスリン投与後には、低血糖などの副作用が生じる可能性があるため、猫の健康状態に注意を払い、異常を感じた場合はすぐに獣医に相談することが重要です。
食事管理
猫の糖尿病治療において、食事管理は非常に重要な役割を果たします。理想的には、低炭水化物で高食物繊維の食事が望ましいとされ、以下の点に気を付けることを推奨します。
- 高タンパク質の食事: 猫は肉食性であるため、高タンパク質の食事が基本です。栄養バランスを考慮した専用の療法食も市場に流通しています。
- 食物繊維の摂取: 食物繊維は血糖値の急激な上昇を抑える働きがあるため、食物繊維が豊富なフードの選択が推奨されます。
- 食事回数の設定: 猫の血糖値が急上昇するのを防ぐため、1日の食事は複数回に分けて与えることが望ましいです。理想的には3回以上に分けることで、血糖値の安定が図れます。
- おやつの制限: 猫のおやつは1日のカロリー摂取量の10%以下に抑え、特に糖質を多く含むものは避け、健康を考慮したおやつを選びましょう。
環境への配慮
猫の糖尿病管理において、食事だけでなく、猫が過ごす環境にも考慮が必要です。ストレスの多い環境は血糖値に悪影響を及ぼす可能性があるため、リラックスできるスペースを提供することが大切です。環境の変化やストレス要因を減らし、猫が快適に過ごせるような工夫を施しましょう。
これらの治療法や食事管理に積極的に取り組むことで、猫の糖尿病をしっかりと管理することが可能になります。適切な治療と環境の整備は、愛猫の健康を守るための第一歩です。

まとめ
猫の糖尿病は深刻な状態になる前に早期発見することが重要です。飼い主の皆さんは、猫の日々の健康状態を注意深く観察し、異変に気づいたらすぐに獣医師に相談することが肝心です。また、適切な食事管理とインスリン療法を組み合わせて、猫の血糖値をしっかりとコントロールすることで、糖尿病の症状を改善し、愛猫の健康的な生活を実現することができます。猫の糖尿病は予防と早期発見、そして適切な治療が何より大切なのです。

よくある質問
猫の糖尿病の主な症状は何ですか?
猫の糖尿病の主な症状は、多飲多尿、体重減少、そして元気の低下です。初期段階では明確な症状が見られない場合もありますが、これらの変化に注意を払うことが重要です。進行すると、嘔吐や下痢、毛並みの悪化など、さらに深刻な症状が現れる可能性があります。
猫の糖尿病の発症リスクはどのような要因がありますか?
猫の糖尿病の主なリスク要因には、肥満、高齢、去勢・避妊手術、ストレス、そして食事内容が挙げられます。特に肥満は大きなリスク因子で、インスリン抵抗性を高めることから、予防のためには適切な体重管理が不可欠です。
猫の糖尿病の診断方法には何がありますか?
猫の糖尿病の診断には、血液検査と尿検査が重要です。血液検査では血糖値やフルクトサミン値を、尿検査では尿糖やケトン体の有無を確認します。さらに、レントゲンやエコー検査などの追加検査を組み合わせることで、より詳細な情報が得られます。
猫の糖尿病の治療法にはどのようなものがありますか?
猫の糖尿病の治療には、インスリン療法と食事管理が重要です。インスリン療法では、適切な投与量と投与方法を見つけることが必要です。食事管理では、高タンパク質・低炭水化物の療法食の選択や、食事回数の設定など、血糖値の安定化に向けた取り組みが求められます。

最新記事 by 大森ペット霊堂 (全て見る)
- 猫のインスリン注射について|糖尿病治療の基礎から血糖値管理まで - 2025年9月22日
- 【必見】亡くなったペットのエンゼルケアのやり方 - 2025年9月6日
- 【ペットの安楽死】飼い主が知るべき正しい判断基準と流れ - 2025年9月2日