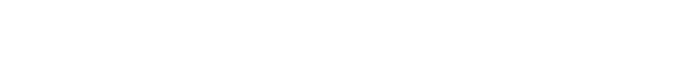【保存版】犬と一緒に防災対策|災害時に守るための準備と避難方法
2025年9月11日

地震・台風・豪雨などの自然災害が多い日本。
「自分の身を守る準備」は進めていても、「犬の防災」まで考えている飼い主さんはまだ少ないのではないでしょうか。
災害時、避難所で「ペット不可」と言われたり、必要な物資が手に入らず困ったりするケースは少なくありません。
また、日頃から準備をしていなかったために犬がストレスで体調を崩す例もあります。
この記事では、犬を飼っている人が災害時に必要な防災対策をグッズ・避難行動・しつけ・情報収集の4つの視点から詳しく解説します。
愛犬の命を守るために、今日からできる準備を一緒に始めましょう。
目次
- 1.犬と暮らす人に必要な防災意識
- 日本は災害大国、ペットの防災が必須な理由
- 飼い主と犬、両方の命を守るために知っておきたいこと
- 2.犬のための防災グッズチェックリスト
- フード・水の備蓄は何日分必要?
- 首輪・リード・ハーネスは予備を用意
- 犬用トイレ用品・衛生用品
- 常備薬・ワクチン証明・健康手帳の準備
- 犬が安心できる毛布・キャリーケース
- 3.災害発生時の犬との避難行動
- 犬と一緒に避難するか、自宅待機か判断基準
- 避難所でのペット受け入れルールを事前に確認
- 車中泊避難の注意点と犬の快適性確保
- 4.犬のしつけと防災の関係
- ケージに慣れさせることの重要性
- 「吠え対策」と「待て・おいで」の基本訓練
- 知らない人や犬との共生に慣れさせる
- 5.災害時に役立つ情報収集とネットワーク
- ペット同行避難を想定した自治体の情報チェック
- 動物病院・ペットホテルの緊急連絡先リスト
- 飼い主同士の防災コミュニティ活用
- 6.飼い主が今すぐできる犬の防災準備
- まとめ|犬と飼い主が安心できる防災を
- よくある質問
- Q1. 犬の防災バッグはどんなものを選べばいいですか?
- Q2. 災害時、犬のストレスを減らすにはどうしたらいいですか?
- Q3. 避難所に犬と一緒に入れるかどうかはどう調べればいいですか?
- Q4. 犬が病気や高齢の場合、防災準備で特に注意することはありますか?
1.犬と暮らす人に必要な防災意識
日本は災害大国、ペットの防災が必須な理由
日本は世界でも有数の「災害大国」です。
内閣府の調査によると、大地震や大型台風の発生確率は高く、誰もが被災する可能性を持っています。
そのため、人間だけでなくペットも含めた「家族全員の防災準備」が必要です。
飼い主と犬、両方の命を守るために知っておきたいこと
犬を助けるのは飼い主であり、飼い主が無事でなければ犬を守れません。
まずは飼い主自身の安全を確保し、次に犬の命を守る行動を取れるようにすることが大切です。

2.犬のための防災グッズチェックリスト
災害時に必要な物資は「人間用+犬用」をセットで考えることが重要です。
フード・水の備蓄は何日分必要?
-
ドライフードや缶詰を最低5日分(できれば7日分以上)
-
犬の飲料水も人間とは別に用意(1日あたり体重1kg=約50mlが目安)
-
開封後の保存に便利なジッパーバッグやタッパーも用意
首輪・リード・ハーネスは予備を用意
避難の途中で破損する可能性もあるため、予備をバッグに入れておくと安心です。
また、必ず**迷子札(飼い主の連絡先入り)**を装着しましょう。
マイクロチップ登録も併せて済ませておくと、万が一の迷子時に役立ちます。
犬用トイレ用品・衛生用品
-
ペットシーツ(1日数枚×1週間分)
-
ビニール袋・消臭袋
-
ウェットティッシュやアルコールシート
-
消臭スプレー
避難所では匂いや衛生面への配慮が必要です。
常備薬・ワクチン証明・健康手帳の準備
-
持病がある犬には処方薬を1週間分
-
ワクチン証明書や狂犬病予防接種票はコピーを防災バッグへ
-
写真(犬と一緒に写っているもの)も準備しておくと、迷子時に役立ちます
犬が安心できる毛布・キャリーケース
避難所では他の犬や人と一緒に過ごすため、キャリーケースやクレートが必須です。
お気に入りの毛布やタオルを一緒に入れておくと、犬が落ち着きやすくなります。

3.災害発生時の犬との避難行動
犬と一緒に避難するか、自宅待機か判断基準
-
建物の損傷が大きい → 避難
-
安全が確認できる → 自宅待機も可能
ただし「避難指示」が出た場合は必ず避難し、犬を置き去りにしないようにしましょう。
避難所でのペット受け入れルールを事前に確認
自治体によって対応が異なります。
-
同行避難(飼い主と一緒に避難可能)
-
同伴避難(建物内の別スペースで飼育)
-
ペット不可(別の場所を探す必要あり)
事前に自治体や動物愛護センターのホームページを確認し、受け入れ可能な避難所を把握しておきましょう。
車中泊避難の注意点と犬の快適性確保
避難所がペット不可の場合、車中泊を選択する飼い主もいます。
しかし、長時間の車中泊には以下のリスクがあります:
-
換気不足による熱中症
-
エコノミークラス症候群(人間)
-
犬のストレスや体調不良
車内温度の管理とこまめな散歩を意識しましょう。

4.犬のしつけと防災の関係
ケージに慣れさせることの重要性
普段からクレートやキャリーに慣れている犬は、避難時のストレスが大幅に軽減されます。
「安心できる場所」としてケージを使えるように訓練しておきましょう。
「吠え対策」と「待て・おいで」の基本訓練
避難所では多くの人が共同生活を送ります。
犬が無駄吠えをしないよう日常的にしつけを行いましょう。
また「待て」「おいで」ができると、安全に誘導できます。
知らない人や犬との共生に慣れさせる
災害時は慣れない環境で、多くの人や犬と接することになります。
普段からドッグランやカフェなどで社会化を進めておくと安心です。
5.災害時に役立つ情報収集とネットワーク
ペット同行避難を想定した自治体の情報チェック
自治体ごとに避難所の運営ルールが異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。
「防災マップ」や「地域の避難所一覧」にペットの記載がある場合もあります。
動物病院・ペットホテルの緊急連絡先リスト
避難所に入れない場合のために、預けられる病院やホテルの連絡先を紙とスマホの両方に保存しておきましょう。
飼い主同士の防災コミュニティ活用
近所の飼い主さん同士で情報交換をしておくと安心です。
「一時的に犬を預かる」など、助け合いのネットワークが命を救うこともあります。
6.飼い主が今すぐできる犬の防災準備
-
家庭での備蓄品の点検(賞味期限チェック)
-
人用と犬用の避難バッグの作成
-
家族全員での避難経路・避難先の確認
-
年1回の「防災訓練」
防災は「準備して終わり」ではなく、定期的な見直しが必要です。

まとめ|犬と飼い主が安心できる防災を
犬の防災対策は、
-
必要な物資の備蓄
-
災害時の行動訓練
-
正しい情報収集とネットワーク
この3つが柱となります。
「うちの犬は大丈夫」と思わず、日頃から準備を整えることが大切です。
災害はいつ起こるか分かりません。
大切な家族である愛犬を守るために、今できることから始めましょう。
よくある質問
Q1. 犬の防災バッグはどんなものを選べばいいですか?
A. 犬用の防災バッグは持ち運びやすく、収納力のあるリュックタイプがおすすめです。
中身は「フード・水・薬・トイレ用品・リード・キャリーケース用の小物」を入れておき、定期的に中身を入れ替えましょう。
Q2. 災害時、犬のストレスを減らすにはどうしたらいいですか?
A. 普段からクレートやキャリーに慣れさせておくことが一番の対策です。
また、お気に入りの毛布やおもちゃを持っていくと安心できます。飼い主が落ち着いて接することも犬にとって大切です。
Q3. 避難所に犬と一緒に入れるかどうかはどう調べればいいですか?
A. 各自治体の防災マップや公式ホームページに記載されていることが多いです。
「同行避難」と「同伴避難」の違いを理解し、最寄りの避難所がどの方式を採用しているかを事前に確認しておきましょう。
Q4. 犬が病気や高齢の場合、防災準備で特に注意することはありますか?
A. 持病がある犬は常備薬・診察記録・かかりつけ病院の連絡先を必ず防災バッグに入れておきましょう。
高齢犬は体力がないため、避難所よりも車や親族宅など静かな環境を優先するのも選択肢です。
wp-tech
最新記事 by wp-tech (全て見る)
- 犬の認知症を徹底解説|初期症状・治療・介護・予防までわかる完全ガイド - 2025年12月15日
- 【保存版】ペット葬儀に宗教は必要?宗教別の供養方法と選び方ガイド - 2025年12月13日
- 【保存版】ペットが見せるストレス行動15選|今日からできる改善法つき - 2025年12月11日